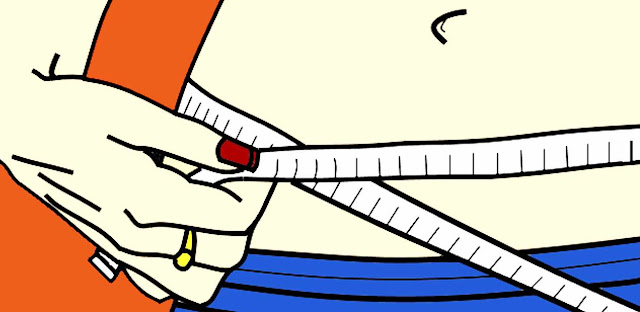【名文に触れる】自信が持てず、悩んでいる人へ(夏目漱石 門下生への手紙より)

他人は決して己以上遥かに卓絶したものではない又決して己以下に遥かに劣つたものではない。特別の理由がない人には僕は此心で対して居る。夫で一向差支はあるまいと思ふ。 (夏目漱石 森田草平宛書簡より一部抜粋) こちらは、夏目漱石が門下生の森田草平へ宛てた手紙の一節です。森田は「自分の生い立ち」に関する悩みを抱えていて、漱石にそれを告白する手紙を書きます。今回紹介した一節は、その手紙に対して漱石が返信したものです。 「他人は自分よりもはるかに優れているわけではなく、また劣っているわけでもない。特別な理由がない人には、そのような考えで向き合っている」 漱石は悩みを抱え、自分に自信が持てないでいる森田に対して、そう伝えていきます。この考え方は、私たちにも大切な視点だと思うのです。私たちは誰かと接する時に、その人に対してまっすぐに向き合うのではなく 「自分(または他者)と比較しながら観察」 してしまいます。 ここは負けた。でもこの部分は私の勝ちだ。無意識ですばやく評価をして上下をはっきりさせたくなるものだと思うのです。そして、 自分の負けを認めることでコンプレックスを強めて しまったり、 相手よりも優れていると考えている部分を必要以上にアピール してしまったりもします。 比較することで「消耗戦」を繰り返さないために しかしそれは結局、 自分自身を消耗させてしまいます。 物事は視点を変えると立場が変化しますし、今までの価値観で判断していると来月にはそれが覆ることもある時代です。 消耗戦ほど不毛な戦いはありません。 そこから何かが生まれることは少なく、ただ時間を浪費してしまったという後悔が残ってしまうものだからです。 誰かと接する時は、狭く偏った自分の評価軸だけで判断するのではなく「相手は自分よりも優れているわけではなく、また劣っているわけでもない」と考えていくことが、様々な視点からも大切になってくるのではないでしょうか。 夏目漱石の「すごさ」とは? 実際に漱石が書いた手紙を読んでいると、相手によって態度を変えることがありません。相手が 子供の読者でも、大人でも門下生でも、相手の自我を尊重して接している ことが伝わってきます。漱石について勉強していくほどに「すごさ」が見えてくる。ぜひ一度、漱石先生に手紙を書いてみたかった。私のような一般人にでも、もしかしたら返信をしてもらえたかもし